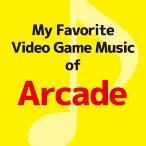こんにちは、こんばんは、コケガエルです。
唐突ですが、ゲームの名曲といえば?…ありすぎて絞れませんよね。すみません。
では、あなたの思い出の一曲は、何の曲ですか?…たくさんありますよね。
僕は、PC-8801mkIISR用のテグザー(GAME ARTS/1985)が、たくさんある内の1曲です。
何が思い出かといえば、初めてのFM音源体験だったから。(※アーケード初のFM音源となる『戦場の狼』がテグザーの1か月後)。
ゲームも衝撃的でしたが、これまでのゲームでは聞いたことのない澄んだ音色が更に衝撃的でした。ゲームオーバー時の「月光」が強烈に記憶に残っています。曲調が暗すぎて(笑)
と、いうわけで(?)
今回から数回にわたって“ゲーム音楽”について、年代を追いながら語っていこうかと思います。そして整理をしながら、個人的ベストを選んでみようかと思った次第です。
今回は、80年代のアーケード限定で3曲。次回はPCゲームで3曲、またその次は家庭用コンソールで3曲という感じで、それぞれ3曲ずつ、合計10曲程度を個人的名曲として挙げてみる予定です。(…ムリかなー?)
今までこんな事は考えたことも無いので、正直どうなるかは分かりません。やってみてダメでしたら曲数を増やすとか内容を変更します。ま、とりあえず書き進めてみましょうー。
あ、先に断っておきますが、僕はゲームミュージックは大好きですが、コレクターでもマニアでもありませんので、CDや音源はほとんど持っておりません。購入した事は…2回だったかな?中学生の時。ほとんどは現場(ゲーセン)で堪能。もしくはカセットテープをダビングさせてもらうでした(笑)
なので、おのずと僕の記憶と経験に基づいた記事になるので、詳しい方には物足りない内容になりそうですが、一緒に懐かしんでもらえると嬉しいです。
ではお付き合いください。ちょっと長めです。
ゲームBGMの創生期(1981年)
ゲームは小学の低学年から遊んでいますが、音楽・曲として意識したのは何からでしょう。
僕のようなピコピコ中年の多くは“NEWラリーX“(namco/1981)で決まりですね。
この頃はまだゲームにBGMというものがほとんどありません。音楽と言えるものはスタート音やファンファーレ程度で、ゲーム中は効果音のみ(+環境をイメージさせる単調な音?)が当たり前の時代でした。
NEWラリーXは、そんな中で2和音のメロディアスなBGMが流れたのですから、ちょっとした事件です。小5の僕が「これは凄い」と驚いた記憶は無いのですが、家でも学校でも「デレレレ、デッテー↑ デレレレ、デッテー↓」と歌っていたことはハッキリと覚えていますから、かなりのインパクトがあったのでしょう。
ゲーム中に曲が流れるという事であれば、前年(1980)に無印のラリーX(namco)、ルパン三世(TAITO)、1979年にはシェリフ(Nintendo)が存在しておりました。しかし、これらのゲームはすべて単音であり、BGMと呼ぶには単調なものでした。なので、本格手なBGM付きのゲームは、NEWラリーXから始まったと言って良いのだと思います。
同年発売のBGM付きゲームとしては、リバーパトロール(ORCA)、フロッガー(KONAMI)等がありました。どちらも大好きで、何度も遊んだゲームです。音も中々のものでした。
BGMは当たり前に…?(1982年)
さて、NEWラリーXの翌年(1982)はディスコNo.1(DECO)、ムーンパトロール(IREM)、ペンゴ(SEGA)、プーヤン(KONAMI)等が印象的です。
ムーンパトロールは、シンプルなメロディーに『タカタカタカタカ…』と淡々とリズムを刻むハイハットの音が印象的。そしてエコーのかかった撃墜音が、独特の雰囲気を出していました。MSXや8001mkII、海外の多くのPCにも移植された人気作です。僕もゲーセンや友人宅で遊んでいた大好きなゲームです。
そしてプーヤン。この頃からコナミのセンスが光っておりました。ぶ厚いパーカッションの音や軽快な曲も素晴らしいのですが、パンパンと割れる風船の音が気持ちいいゲームでした。この時期に限れば、僕の中での『音楽が良いゲーム』No.1でした。ノリノリ。
ペンゴはゲーム自体も名作でしたね。ダイヤのブロックを3コ並べる面白さを知ってから、俄然熱中しました。人気があったので、ゲームセンターにいると、いつもペンゴの音が耳に入ってきていましたよ。なので夜、眠るときに、敵(スノービー)が生まれる「ビューイ↑」やシビれた時の「ビヤヤヤーン」という効果音が頭の中で鳴り続け、安眠を妨害するのです(笑)
1982年は、まだBGMの“あり”、“無し”の比率は、まだまだ“無し”の方が多かったと思います。基盤の設計や作曲できる人の確保、生産・販売を考えると、境目の年だったのかな?
やはりメーカーによって差がでますよね。この時に結果を出せているナムコ・コナミ・セガ(ペンゴはコアランドですが)は流石といったところでしょうか。
中から妖精こんにちは(1983年)
おまたせしました!1983年は、何といってもロックンロープ(KONAMI)、マッピー、リブルラブル(namco)の登場です。
ロックンロープはPSG×2、マッピー・リブルラブルは波形メモリ音源です。波形メモリ音源はPSGと認識されている方もおりますが、PCM音源に似た原理で、PSGよりも音色の自由度が高い音源です(PCMに比べるとかなり単純ですけどね)。マッピー・リブルラブルの厚く“パンッ”と張りのあるサウンドは最高でした。前年までに発売されたゲームに比べると表現力が段違いです。
ロックンロープの曲自体は、控えめであまり主張しない抑えたBGMでしたね。しかしプーヤンと同じPSG×2の音源が奏でるブ厚いスタート音と面クリア時のサウンドは子供ながら良い音と感じました。
マッピー・リブルラブルは凄く良いです!大好き。この頃(以降数年)のナムコは、ゲームデザイン・グラフィック・音楽、どれをとってもセンスが頭抜けていて、この3つが融合したナムコのゲームは他社の追随を許しませんでした。当時ナムコがスポンサーだった『ラジオはアメリカン』(通称ラジアメ)がゲーム少年の間では大人気で、僕も毎週楽しみにしておりました。その中で放送されたリブルラブルのCMを覚えている方、多いのではないでしょうか。忘れられませんよね(笑)
マッピー、リブルラブルの作曲者は大野木 宜幸(おおのぎ のぶゆき)さんという方で、他にもポールポジションIIやメトロクロスなどを作曲した人です。どれも記憶に残る曲ですよね。
後にギャプラス・ドルアーガの塔・スカイキッドなどの名曲を作った小沢純子さんも、この年にナムコに入社しております。
この年のパック&パル、ジッピーレースも思い出深いゲームで、音楽もよく覚えていますが、サウンドの完成度という点では上記の3タイトルには一歩及ばずです。
もう挙げ出したらキリが無い(1984年~)
1984年以降は、ゲームにBGMは当たり前となりました。1年間に発売されるタイトル数も急速に増加していきますので、ここからは特に強く印象に残っているタイトルだけ、ざっと挙げて行きます。
1984年
ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険(データイースト)
ギャプラス(namco)
ドルアーガの塔(namco)
パックランド(namco)
ソンソン(CAPCOM)
新入社員とおるくん(KONAMI)
エクイテス(SEGA/アルファ電子)
エクイテスは独特なエレクトーンのような音色でしたね。ちょっと悪い意味で印象に残っています。新入社員とおるくんもパンチのあるサウンドで好印象ですが、この中ではドルアーガの塔が一番好きです。特にクオックスの面の曲が重厚で大好きでした。
1985年
ASO (SNK)
T・A・N・K (SNK)
テラクレスタ(Nichibutsu)
スカイキッド(namco)
ドラゴンバスター(namco)
メトロクロス(namco)
セクションZ(CAPCOM)
グラディウス(KONAMI)
ツインビー(KONAMI)
スペースハリアー(SEGA)
青春スキャンダル(SEGA/コアランドテクノロジー)
この中では、セクションZ・青春スキャンダルが個人的ツボですが、スペースハリアーの完成度には敵いません。しかし、ここは人生でいちばん100円玉を投入したグラディウスを推しましょう。4面(逆火山)も捨てがたいのですが、6面(細胞)の曲が大好きです。
↓6面は【5:38】から。
1986年
源平討魔伝(namco)
サンダーセプター(namco)
トイポップ(namco)
ホッピングマッピー(namco)
闘いの挽歌(CAPCOM)
沙羅曼蛇(KONAMI)
アウトラン(SEGA)
カルテット2(SEGA)
ファンタジーゾーン(SEGA)
ダライアス(TAITO)
ラッシュ&クラッシュ(CAPCOM)
うむむむ。雰囲気はサンダーセプター、音色ではホッピングマッピー、いちばん聴き込んだのはアウトラン、大好きなのはファンタジーゾーン、個人的ツボはラッシュ&クラッシュ、聴いたことがない人に聴かせたいのはカルテット2です(笑)。
いやーまいった。もう絞るのが難しくなってきました。しかしここは聴いた回数でアウトランですね。いささか捻りのない選択ですがしょうがないです。
1987年
R-TYPE(IREM)
ドラゴンスピリット(namco)
ワンダーモモ(namco)
A-JAX(KONAMI)
アフターバーナーII(SEGA)
ライフフォース(KONAMI)
ニンジャウォーリアーズ(TAITO)
ドラスピのシンセドラム、A-JAXのオーケストラヒットも印象的ですが、なんと言ってもアフターバーナーIIですよね。間違いないです。…同年にライフフォースが無ければ。くそう。
前年の沙羅曼蛇のときには、ステレオのFMは凄いと思いましたが、音色や曲は特に良いとは思っていなかったんです。しかし沙羅曼蛇の海外版であるライフフォース、その2面の曲「Thunder bolt」がもうカッコよくてツボすぎて、一発でまいっちゃいました。こんなに短いループ曲なのに、なぜこんなにもドラマチックな曲が書けるのかと感動しました。
1988年
オーダイン(namco)
メタルホーク(namco)
グラディウスII -GOFERの野望-(KONAMI)
ギャラクシーフォースII(SEGA)
サイバリオン(TAITO)
大魔界村(CAPCOM)
この頃になると、ほとんどがFM+PCM音源って感じですよね?こうなると“抜きん出てコレ!”ってのがあまりなくなってきます。技術的にはほぼ横並びですから、あとは好みの問題ですよね。この中では、ゲーム音楽には珍しいスラップベースと、リアルなパーカッションが印象的なギャラクシーフォースIIでが好きでした。緩やかな曲と激しい曲の緩急が凄く良いです。(後半面は残念な部分もありますが…)
1989年
ここまでゲーム音楽のレベルが上がると、逆にしぼりやすいですね。1989年は僕の中ではワルキューレの伝説(namco)一択です。他にもダライアスIIなどもありましたが、全体のレベルが高い中でもワルキューレの伝説は、ちょっと格がちがうといか名曲と呼ぶにふさわしい出来でしたね。
作曲者は川田 宏行(かわだ ひろゆき)さん。妖怪道中記(1987年)やギャラガ’88(1987年)の作曲を担当された方です。
ざーっと80年代を駆け抜けた感じですが、自分でも驚きの長文になってしまいました。現時点では当ブログの最長記事です。
では、この中から偏見と独断のによるマイベスト3曲を選びたいと思います。
アーケード部門まとめ
最高の一曲:ライフフォース(KONAMI/1987)から2面「Thunder bolt」
思い出の一曲:グラディウス(KONAMI/1985)から6面「Mechanical Globule」
一番聴いた一曲:アウトラン(SEGA/1986)から「Splash wave」
一曲ずつコメントを書こうかとも思ったのですが、それぞれ動画を貼っておりますので、聴いてもらえれば説明不要かと思いましたので、あえて書きません。百聞は一聴に如かずです。
…しかし選んだコナミの2曲が、同じ作曲者(東野美紀さん)になるとは自分でも予想外でした。
自分で自分の事は“ナムコ・セガ好き”と思っていたのですけどねー。勘違いだったのでしょうか?まさかのコナミですよ。(いやコナミも好きですけどね。特にFC・MSX時代は)
それでも、僕のアーケードゲーム音楽のヒーローは川口博史(Hiro師匠)さんで変わりないです。スペースハリアー、ファンタジーゾーン、アウトラン、アフターバーナーの作曲をされたという実績はゲーム史に燦然と輝やいております。
ただ、僕がThunder boltを好きすぎただけの事なんです…密度がすごいのに無駄が無いというか…僕の中で『完璧』とか『完全』といえる曲なんですよね。褒めすぎでしょうか。ま、あくまで僕個人の好みですから。
はー。とりあえず自分の中でのアーケードのゲーム曲ベスト3が決まりましたが、自分が驚く結果となりましたね。
割と有名どころばかりで申し訳ない感じですが、北海道の田舎に住んでいたので、あまりマイナーなゲームは設置が無かったのです。すみません。
きっと僕の知らない隠れた名曲は沢山あるのでしょうね。「これは聴いておけよ」というのがあれば、ぜひ教えてください。
次はパソコンゲームか家庭用コンソールか…ちょっと間隔が空くかもしてませんが、それぞれのマイベスト曲を選んでみたいと思います。
ではでは。